ワインコラム第23回【戦国武将とワインの物語〜織田信長編〜】
「信長がワインを飲んでいた」
そう聞くとちょっとロマンがありますよね✨
実際のところ、信長がワインを飲んだという確実な記録は残っていません
ですが、"その可能性がとても高い"と言われる理由を信長の性格とともに深掘りしていきます

こちらのマダムグログでは、生活に役立つワインに関する情報を月3回お届け
🍷マダムのワインコラム🍷
毎月2日、12日、22日の月3回更新です
✝️宣教師とのつながり
信長はキリスト教の布教を認め、ルイス・フロイスなどの宣教師たちを保護していました
彼らはミサ(宗教儀式)でワインを使うため、信長の前でも登場していた可能性があります

つまり、「飲まなかったとしても、ワインを見た」ことは確実でしょう
そして、宣教師たちはワインをミサで使う聖なる飲み物として大切にしており、信長もその特別さを理解していたと考えられています
信長はキリスト教そのものを信仰した訳ではありませんが、宣教師の教養や秩序、外交力には敬意を払っていました
仏教勢力を抑える上でも、西洋文化や宣教師を巧みに利用したとも言われています
⚓️南蛮貿易と"ぶどう酒"
16世紀の日本には、ポルトガル船を通じてワインが入ってきていました
「ぶどう酒」という名前で記録にも残っており、堺や長崎では取引もあったようです
まだ嗜好品というよりも薬酒のような扱いでした
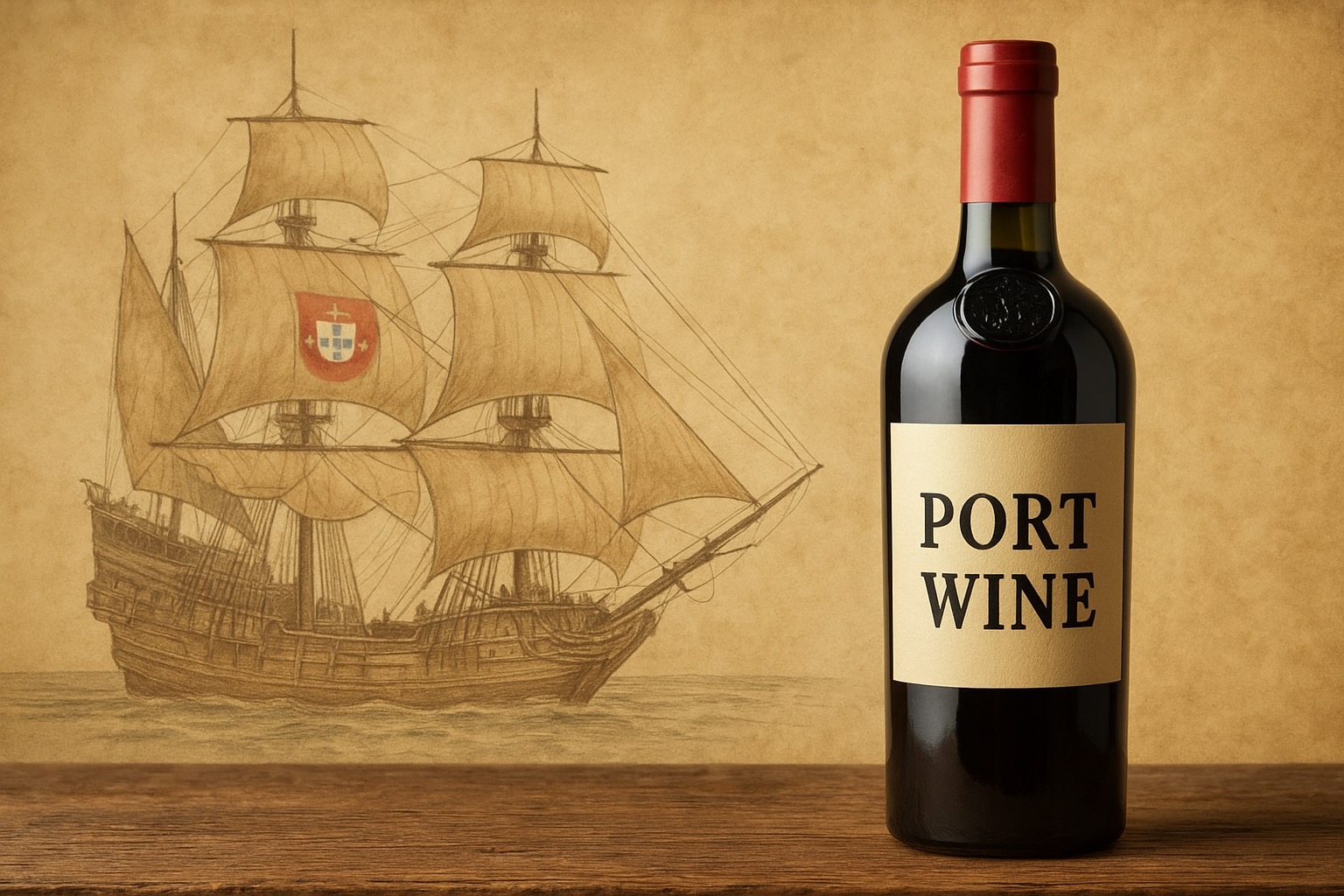
そして信長といえば、1543年に種子島に伝わった火縄銃などの西洋の武器に関しても、すぐに取り入れ戦術を変えた人物。
南蛮文化に強い関心を持っていた信長が、その珍しいお酒を試さなかったとは考えにくいですよね
🏯信長の美意識と嗜好
金箔の茶室、派手な装束、そして南蛮趣味
信長は"他の誰よりも新しいもの"を愛するタイプでした
南蛮から伝わった金細工、ステンドグラス、絵画、装飾品にも強い関心を持っていました

新しいものを取り入れる柔軟さと美的感覚を持ち合わせた信長なら、ワインのような飲み物にもきっと好奇心をくすぐられたはず✨
そうした性格を考えると、異国のワインにも興味を示したとしても不思議ではありません
🍷まとめ
確かな記録として「信長がワインを飲んだ」とはいえませんが、「ワインを目にし、口にした可能性が非常に高い戦国武将」という見方が、歴史研究の中では一般的です
信長は常に時代の一歩先を行く人
ワインを通じて"新しい文化の香り"を感じ取っていたと想像すると、まさに信長らしいエピソードです

南蛮人との交流を深めるのにワインを嗜んだ家康
革新的で新しいものを受け入れる柔軟さがあった信長
次回は豊臣秀吉とワインの関係についてお届けします
信長と対照的な「秀吉らしいワインとの付き合い方」に注目です!
Cheers to a wonderful wine life !
